
はじめての小説⑧「小道具・大道具を使う」
脚本の視点から、大道具・小道具の使い方を考えます。

脚本の視点から、大道具・小道具の使い方を考えます。

キャラクターやテーマを表す「イメージアイテム」についてのヒントです。

オリジナリティを出すということは、クリシェを避けるということと同じです。

書き終わったあとの「推敲」について考えます。

これまでの「主人公」「事件」「オチ」をログラインという観点からまとめておきます。

今回は物語の終わらせ方を考えてみます。

「事件」という視点から、書くヒントを考えます。

「主人公」という視点から、書くヒントを考えます。

読書会で使用している資料です。
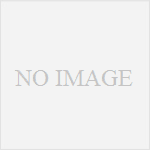
教科書に載っている有名な作家の作品だからってすごいとは限らないし、無名のネット小説だってバカにしてはいけないのです。人の思想や感情に「上下」はないからです。作者も読者も同じ人間です。